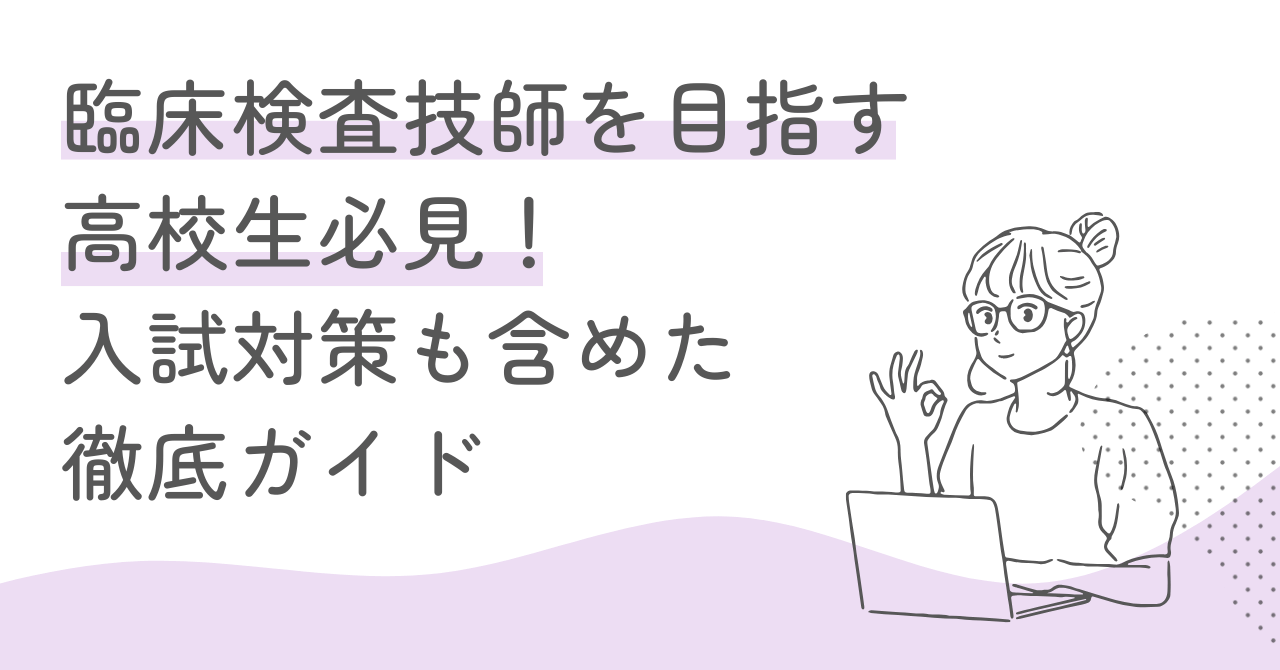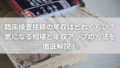臨床検査技師は、病院や研究機関で検査を行い、病気の診断や治療に重要な役割を果たす医療専門職です。
臨床検査技師になるためには、大学や専門学校の「臨床検査技師養成課程」に進学し、国家試験に合格する必要があります。
本記事では、臨床検査技師養成学校の受験を目指す高校生向けに、受験科目の勉強法や共通テスト対策、面接・小論文の準備ポイントを詳しく解説します。
しっかり準備をして、合格を勝ち取りましょう!
1. 臨床検査技師養成学校の入試方式

臨床検査技師を養成する学校は、大学・短期大学・専門学校の3種類があります。
学校によって入試方式は異なりますが、一般的な入試方法は以下の通りです。
1. 一般入試(大学・専門学校)
大学や専門学校で実施される独自の学力試験です。
一般的に、英語・数学・理科(生物または化学)が出題されます。さらに小論文と面接がある学校もあります。
学校によっては共通テストの受験が必要な場合と、必要でない場合があるので、自分が行きたい学校はどのタイプなのかを確認しておきましょう!
国公立の大学を目指している人は、選択肢を広げるためにも共通テストを受けることを前提に学習を進めることをおすすめします。
2. 推薦入試(指定校推薦・公募推薦)
推薦入試では、評定平均や面接、小論文が重視されます。
推薦を狙う場合は、高校の成績をしっかり管理し、志望動機を明確にすることが重要です。
推薦入試は倍率が高いので、対策はしっかりと行う必要があります。
また、受験時期が早いのでオープンキャンパスなどを利用して、面接で話せる内容を事前に準備できていると、焦らずに受験に臨めるでしょう。
3. AO入試
学力試験よりも、面接や志望理由が重視される入試方式です。
「なぜ臨床検査技師になりたいのか?」を明確にし、将来の目標や適性をアピールできるよう準備しましょう。
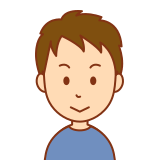
AO入試は専門学校や私立大学が多いね!
専門学校と大学どっちが良いか悩んでいる人はこちらもチェック!
➤臨床検査技師を目指すなら大学?専門学校?徹底比較して最適な進路を選ぼう!
2. 共通テスト対策(国公立・一部私立大学向け)
共通テストを利用する大学を受験する場合、科目ごとの勉強法を工夫することが重要です。
今回は、英語・数学・理科(生物・化学)に絞って説明していきます。
1. 英語(リーディング・リスニング)
共通テストの英語は、文章量が多く、速読力が求められるのが特徴です。
- 長文読解の練習をする(毎日1つは長文を読む)
- 文法・語彙を固める(単語帳・文法書を活用)
- リスニング対策をする(毎日10分は英語音声を聞く)
よりハイレベルな大学を目指したい方は、YouTubeなどで英語のプレゼンテーションの動画を見るとだんだん耳が英語に慣れてくるのでおすすめ!
2. 数学(数学ⅠA・ⅡB)
共通テストの数学は、思考力を問う問題が多いため、計算力だけでなく応用力も鍛えましょう。
- 基本的な公式をしっかり覚える
- 時間を計って模試形式で解く
- 苦手な分野を早めに克服する(特に図形・確率・数列)
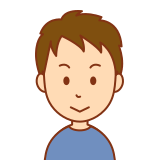
数Ⅲって必要じゃないの?
こんな疑問を持つ方もいるかもしれません。
理系に進んだら悩ましいのが数Ⅲを勉強するかどうかですよね…実は私も数Ⅲはすごく苦手でした(笑)
実際に数Ⅲが必要となってくるのは、一部の国公立大学の二次試験です。
そのため、二次試験で数Ⅲの問題が出ない学校を目指す予定の方は、無理に数Ⅲを勉強する必要はないと思います。
3. 理科(生物・化学)
臨床検査技師を目指すなら、生物・化学の得点をしっかり取ることが重要です。
生物
- 細胞・遺伝・代謝・生態などの基礎知識を固める
- グラフや図の問題に慣れる
- 共通テスト形式の過去問を解く
化学
- 理論化学(化学反応式・モル計算)をマスターする
- 無機・有機化学の暗記を徹底する
- 計算問題を毎日練習する
生物と化学に関しては、学校に入ってからも1年生の時に基礎勉強もあります。
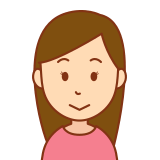
物理専攻だとだめなのかな…?
人によっては高校で生物ではなく物理を選んだという人もいるでしょう。
もちろん、物理専攻でも大丈夫です!
ちなみに臨床検査技師養成学校では、必ず医用工学という物理に知識が必要な分野を学ぶので、物理専攻の人はその時に有利になるはずです!
3. 一般入試の対策
大学や専門学校の一般入試では、英語・数学・理科の3教科が中心です。
学校ごとに出題傾向が異なるため、過去問を解いて対策しましょう。
- 英語 → 共通テストと同様に長文読解と文法対策を重視
- 数学 → 計算ミスを防ぎ、正確に解く練習をする
- 理科(生物・化学) → 実験・計算問題に対応できるようにする
4. 面接・小論文の対策
推薦入試やAO入試では、面接や小論文が重要になります。
1. 面接対策
よく聞かれる質問とその対策を準備しておきましょう。
【よくある質問】
面接では、明確で具体的な答えを用意し、はっきりと話すことが大切です。
また、個人的なおすすめは、オープンキャンパスに行くことです。
学校側も誰がオープンキャンパスに来たかは把握しているので、そこで少しでも印象に残っていると「あの子来てくれたんだ!」と面接の際にも好印象となります。
面接ではいかに面接官の印象に残るかがポイントになってくるので、エピソードはありきたりなものではなく、具体性と自分にしか話せない部分を盛り込むようにしましょう!
2. 小論文対策
小論文では、「医療の役割」「臨床検査技師の重要性」といったテーマが出されることが多いです。
【対策のポイント】
- 序論→本論→結論の構成を意識する
- 医療ニュースをチェックする
- 過去問を使って練習する
その時に話題となってることがテーマになるときもあります。
以下は過去に出題されたことのあるテーマの一例です。実際には、もっと長文で状況説明の文章が記載されていると思います。
そのため、何を聞かれていて、どういう意図でこれが出題されているかを読み解けるようにしておきましょう。
【過去の出題テーマ】
5. 受験勉強のスケジュール
1. 高校2年生までにやるべきこと
- 共通テストの基礎を固める
- 定期テストで良い成績を取る(推薦対策)
- 志望校の入試方式を調べる
推薦入試では、内申点は非常に重要です。高校3年生から頑張っても大幅に上げることは厳しので、基本的に定期テストはおろそかにせず、しっかりと点数を取るようにしましょう!
そして、自分の行きたい学校を少しずつ探していくと、高校3年生の時に志望校探しで焦ることはないはずです。
2. 高校3年生のスケジュール
| 時期 | やること |
|---|---|
| 4〜6月 | 基礎固め(英語・数学・理科) |
| 7〜9月 | 応用問題・過去問演習 |
| 10〜12月 | 模試・小論文・面接対策 |
| 1〜3月 | 最終確認、試験本番 |
各個人の受験方法によって、このスケジュールも変わってくると思います。
そのため、自分で上記のような計画をなんとなくでよいので、書き出してみましょう!
そして、目標を達成するために必要なステップを自分で理解できるようになれば、合格への道が一歩近づくはずです!
まとめ
臨床検査技師養成学校の受験では、共通テスト対策、一般入試対策、推薦・AO入試の準備が必要です。
特に、英語・数学・理科の勉強は重要なので、早めに対策を始めましょう。
臨床検査技師になることも重要ですが、どの学校で学ぶかもその人の人生にとって重要なポイントだと思います。
そのため、しっかりと計画的に勉強し、夢を叶えるために頑張りましょう!