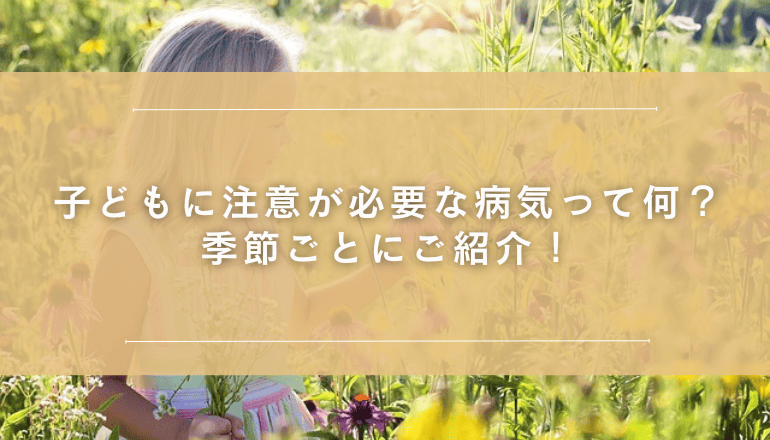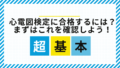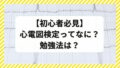子どもは成長過程でさまざまな病気にかかります。特に季節の変わり目は、流行しやすい病気が多く、保育園や学校といった集団生活の場で、病気をもらうことも少なくありません。突然の発熱や発疹に「大丈夫かな?」と心配になることも多いですよね。
今回は、春、夏、秋、冬、それぞれの季節ごとにかかりやすい病気と、対策や予防方法をお伝えします。ぜひ参考になさってくださいね。
【春に注意すべき病気】

春は、気温が上昇し始めると同時にウイルスや細菌が活発になり、感染症が広がりやすい季節。この時期は、学校や保育園での集団生活を通じて病気をもらいやすくなるため、予防策が重要になります。
溶連菌感染症
溶連菌感染症は、春に流行しやすい病気の一つ。溶連菌が咽頭や扁桃に感染し、発熱や喉の痛み、発疹を引き起こします。飛沫感染のため、幼稚園や小学校などでの集団感染に注意しましょう。
主な症状
高熱、激しい喉の痛み、全身のだるさなど。特に喉の痛みが強く、飲食が困難になることも。また、「苺舌」と呼ばれる舌に赤い斑点が現れる特徴的な症状が見られたり、発疹が全身に広がることもあります。
治療と予防
溶連菌感染症の治療には抗生物質が効果的。しかし、服用を途中で止めると合併症を引き起こすリスクが高まるので、決められた期間しっかりと服用しましょう。また、手洗いやうがいを徹底し、タオルや食器などの共有は避けましょう。
麻疹(はしか)
麻疹は非常に感染力の強いウイルス性の病気。春から初夏にかけての流行が多く、ワクチン未接種の子どもや、免疫力が低い小さな子どもがかかりやすいと言われています。麻疹ウイルスは、空気感染や飛沫感染で広がり、感染すると発熱や全身に広がる発疹が現れます。
主な症状
高熱、咳、鼻水、目の充血といった症状から始まります。その後、口内に白い斑点(コプリック班)が現れます。熱がいったん下がり、再び高熱が出ると、今度は赤い発疹が。さらに高熱が続いた場合、肺炎や脳炎といった重篤な合併症を引き起こすことも。特に、免疫力が弱い乳幼児は重症化しやすいため、早期に医療機関を受診しましょう。
治療と予防
現時点で麻疹に有効な治療薬はなく、発熱や咳などの症状を緩和するための薬を服薬する対症療法が中心となります。また、麻疹の予防には、予防接種(MMRワクチン)が最も有効とされており、1歳(第1期)と小学校入学前(第2期)の2回の予防接種が推奨されています。
【夏に注意すべき病気】

夏は気温と同時に湿度も上がり、ウイルスや細菌がさらに活発に活動する季節。水遊びの機会が増えるため、プールでの感染症にも注意が必要です。熱中症や食中毒にも気をつけましょう。
手足口病
コクサッキーウイルスやエンテロウイルスによるウイルス性感染症、手足口病。感染力が強く、乳幼児に多く見られ、手足や口の中に痛みを伴う発疹や水疱ができるのが特徴です。
主な症状
軽い発熱が見られた後、手のひらや足の裏、口の中に小さな水疱や発疹が現れます。口内の発疹は痛みを伴うことが多く、食欲不振や発熱を伴うことも。通常、1-3日で解熱しますが、発疹が治まるまでの間は感染力があるため、集団生活での感染拡大に注意が必要です。
治療と予防
特効薬はなく、症状に応じた対症療法が行われます。脱水症状を防ぐために水分補給はこまめに!予防としては、手洗いや消毒、タオルや食器の共有を避けることが効果的です。
プール熱(咽頭結膜熱)
プール熱は、夏に流行するアデノウイルスによる感染症で、主症状は、発熱、喉の痛み、結膜炎。特にプールでの水遊びを通じて感染が広がることが多いため、子どもたちが感染しやすい病気です。
主な症状
38度以上の高熱が3-5日間続くことがあり、同時に喉の痛みや目の充血が見られます。結膜炎による目の充血や目やにが特徴的で、喉の痛みにより、食欲が低下することも。飛沫感染や接触感染で広がり、特にプールや学校での集団感染が発生しやすいため、感染拡大を防ぐための対策が重要です。
治療と予防
喉の痛みや発熱などの症状に対しては、服薬による対症療法が行われます。また、目の充血や目やにに対しては、抗菌目薬が処方されることも。予防策としては、プール利用後のシャワーを徹底し、タオルやゴーグルの共有は控えましょう。また、プール後は目や喉の異変に注意し、異常が見られた場合は早めに医師の診察を!
ヘルパンギーナ
夏から秋にかけて多く見られ、流行のピークが7月に見られるヘルパンギーナ。コクサッキーウイルスによる感染症です。特に4歳以下の乳幼児に多く見られます。症状は手足口病と似ていますが、口内にできる水疱が特徴的です。
主な症状
突然の39℃以上の高熱で始まり、続いて喉の奥に痛みを伴う水疱が現れます。そのため飲食が困難になり、食欲が低下することも。発熱は数日で下がることが多いですが、喉の痛みが続くため、症状が落ち着くまでには1週間程度かかることがあります。
治療と予防
ヘルパンギーナには特効薬がないため、対症療法が行われます。発熱が続く場合は解熱剤を使用し、十分な水分補給を行うことが大切です。予防策は、手洗いやうがいを徹底し、家庭内での感染拡大を防ぐための対策を講じましょう。
【秋に注意すべき病気】

秋は気温が下がり始め、空気が乾燥してくる季節。この時期は、呼吸器系の病気やアレルギー症状が悪化しやすく、またインフルエンザの流行も始まります。
・インフルエンザ
秋から冬にかけて流行するウイルス性の病気、インフルエンザ。症状は、発熱、頭痛、咳、喉の痛み、筋肉痛など、全身に渡ります。特に子どもは、脳症を併発すると重症化することがあるため、早めの予防接種が推奨されています。
主な症状
主な症状は、突然の高熱、激しい頭痛、全身の筋肉痛や関節痛など。また、咳や喉の痛み、倦怠感が強く、ひどくなると食欲不振や脱水症状を引き起こすことがあります。子どもがインフルエンザにかかると、重症化するリスクが高いため、特に注意が必要です。
治療と予防
治療には抗ウイルス薬が使用され、また、早期に治療を開始することで、症状の重症化を防ぐことができます。特に、幼児や小学生は集団生活を送るため、感染リスクが高く、予防接種を受けることで感染を防ぐことができます。また、手洗いやうがい、マスクの着用を徹底しましょう。
・マイコプラズマ感染症
マイコプラズマ感染症は、夏から秋にかけて流行する呼吸器系の感染症です。細菌の一種で、発熱、咳、喉の痛みなどの初発症状が現れ、咳が徐々にひどくなるのが特徴です。
主な症状
初期には風邪と似た症状が見られますが、次第に咳が激しくなり、特に夜間や運動後に咳がひどくなることも。熱は37度から38度程度の微熱が続くことが多いですが、子どもによっては高熱が出ることもあります。咳が長引くため、肺炎に進展することもあり、注意が必要です。
治療と予防
マイコプラズマ感染症の治療には、抗生物質が効果的です。症状が軽い場合でも、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けることで、合併症を防ぐことができます。予防としては、風邪の予防と同様に、手洗いやうがいを徹底し、体調管理をしっかりと行うことが大切です。
・喘息
喘息は、秋に症状が悪化しやすい呼吸器系の病気です。気温の変化や空気の乾燥、花粉やハウスダストなどのアレルゲンが増えることで、喘息の発作が誘発されやすくなります。寒暖差が激しい夏の終わりから秋にかけての時期は特に注意しましょう。
主な症状
主な症状には、咳、息切れ、喘鳴(呼吸時にゼーゼー音がすること)などがあります。特に夜間や朝方に症状が悪化することが多く、睡眠不足や疲労が蓄積しやすくなります。症状がひどくなると、呼吸が困難になることもあり、緊急の医療対応が必要です。
治療と予防
喘息の治療には、吸入薬や飲み薬が使用されます。発作を予防するためには、定期的に吸入薬を使用し、医師の指示を守ることが重要です。また、アレルゲンを避けるために、部屋を清潔に保ち、特に布団やカーペットの掃除を徹底することが推奨されます。外出時にはマスクを着用し、花粉やハウスダストを吸い込まないように注意しましょう。
【冬に注意すべき病気】

冬は気温が低く、空気が乾燥する季節。風邪やインフルエンザ、胃腸炎などが流行しやすくなります。また、寒さや乾燥による呼吸器系の病気や皮膚トラブルも増加します。
・RSウイルス感染症
冬に流行しやすく、特に乳幼児がかかりやすい病気です。RSウイルスに感染すると、発熱、咳、鼻水などの症状が現れ、場合によっては重篤な呼吸困難を引き起こすことも。特に、生後6か月以内の赤ちゃんは重症化しやすいため、感染予防のために人混みを避けることが推奨されます。
主な症状
主な症状は、発熱、咳、鼻水。症状が進行すると、喘鳴や呼吸困難が現れ、乳幼児の場合は入院加療が必要になるケースも。呼吸困難が見られる場合は、すぐに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
治療と予防
RSウイルス感染症には特効薬がないため、症状に応じた対症療法が行われます。加湿器を上手に利用し、呼吸しやすい体位でゆっくり体を休めましょう。また、感染を予防するためには、手洗いや消毒を徹底し、特に感染のリスクが高い乳幼児がいる家庭では、家庭内での感染拡大を防ぐための対策を講じましょう。
・胃腸炎(腸管感染症)
冬に流行しやすい、ノロウイルスやロタウイルスなどが原因の胃腸炎。嘔吐や下痢が主な症状で、特に小さな子どもは脱水症状に注意が必要です。集団生活を送る保育園や幼稚園での感染が広がりやすいため、感染予防を心がけましょう。
主な症状
主な症状は、突然の激しい嘔吐や水様性の下痢。これに加えて、発熱や腹痛が見られることもあります。特に乳幼児は脱水症状を起こしやすいため、食欲が低下したり、水分が取れなくなった場合は、ためらわずに医療機関の受診を!脱水症状の兆候である、口の渇き、尿の減少、ぐったりとした様子に注意してくださいね。
治療と予防
胃腸炎の治療は、主に対症療法です。無理に食事を取らせることは避け、電解質を含んだ飲料を少量ずつ飲ませることで、脱水症状を予防します。また、ロタウイルスに対しては、予防接種(任意)が有効です。衛生管理の徹底も重要で、しっかり手洗いを行い、食器の共有を避けるなどの対策を行いましょう。特に、ノロウイルスはアルコール消毒が効かないため、流水での手洗いが推奨されています。また、感染者の嘔吐物や排泄物に触れる際は、使い捨て手袋の使用を徹底しましょう。
まとめ
季節ごとに気をつけるべき病気は異なりますが、共通して言えるのは、早期発見と適切な対応が重要だということ。子どもは免疫力が弱く、重症化しやすいリスクが高いからこそ、季節の変わり目や流行が予想される時期には、特に注意を払っておきたいですよね。日々の健康管理をしっかり行い、子どもたちが元気に過ごせる環境を整えていきましょう。
※この記事の内容の一部は、日本小児科学会の「学校、幼稚園、認定こども園、保育所において予防すべき感染症の解説」に基づいています。詳細な情報や最新のガイドラインについては、日本小児科学会の公式資料をご参照ください。