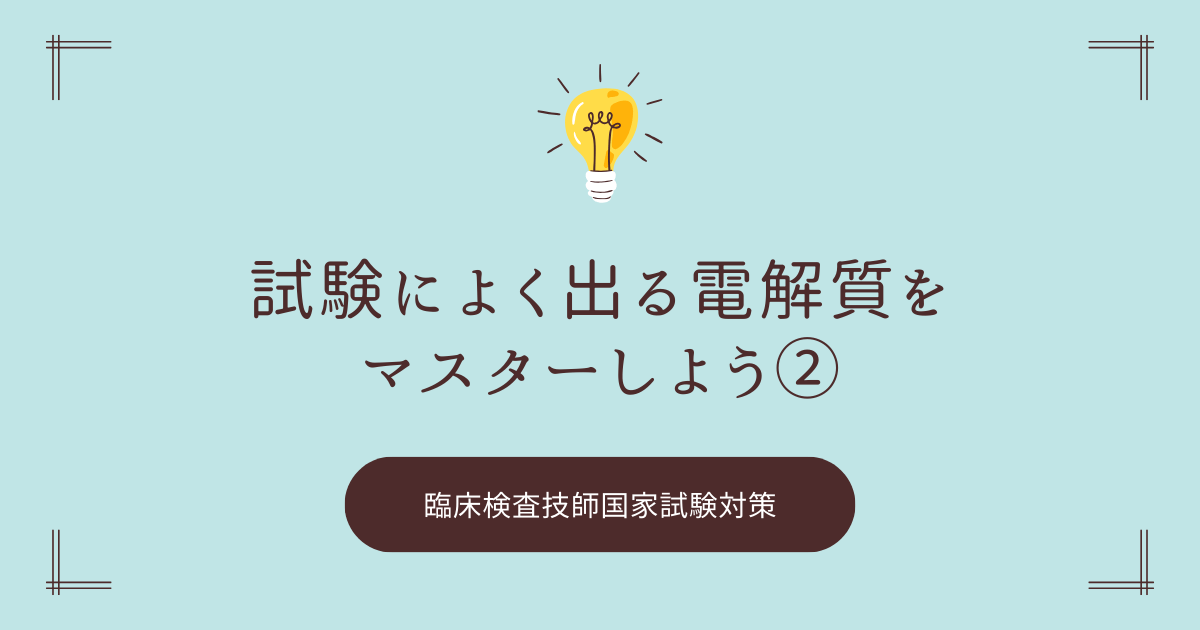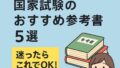国家試験や学校のテストでもよく出題される主な電解質について、今回は、Ca(カルシウム)、Mg(マグネシウム)の2つを詳しく解説していきます。
重要な部分は赤字にしているので、必ずチェックしてメモしてくださいね!
ポイントをおさえて、苦手を克服していきましょう!
Ca(カルシウム)について

ではまず、Ca(カルシウム)について解説していきます。
Caは、骨格を形成する役割や、血液凝固、神経の興奮、心臓の収縮、酵素の活性化に関与しています。
- 基準値:9-11mg/dl
- パニック値:6mg/dl以下、または12mg/dl以上
Caは、骨ではリン酸カルシウムとして存在しています。
一方、血清中のCaはイオン化型(約50%)、蛋白結合型(約40%)、非イオン型の重炭酸塩など(約5-10%)の大きく3つに分けられます。
蛋白結合型は、蛋白質である「アルブミン」と結合してます。そのため、蛋白濃度・アルブミン濃度に影響を受けます。よって以下の2つのポイントは押さえておきましょう!
- 高蛋白血症では見かけ上血液中のCaは上昇↑
- 低アルブミン血症では見かけ上血液中のCaは低下↓
さらに、低アルブミン血症(アルブミン4g/dl以下)の時は、見かけ上血液中のCa濃度は低下するため、補正を行う必要があります。計算式は以下の通りです。
補正Ca濃度(mg/dl)=血清Ca濃度(mg/dl)+{4-血清アルブミン濃度(g/dl)}
このCaの補正式は、国家試験だけでなく、実際の医療現場でも必ず知っておくべきことなので、しっかりおぼえておきましょう!
Caの代謝を調整するホルモン
Caを調整する主要なホルモンは、以下の3つです。
- 副甲状腺ホルモン(PTH)
- ビタミンD₃
- カルシトニン
| ホルモン名 | 関係する臓器 | 作用 | 血中Ca濃度 |
| 副甲状腺ホルモン(PTH) | 副甲状腺 | 骨からのCaの溶出 | ↑ |
| ビタミンD₃ | 腎臓 | 腸からの吸収を促進 | ↑ |
| カルシトニン | 甲状腺 | 骨溶解を抑制 | ↓ |
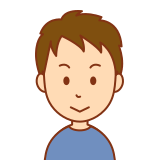
ホルモンとCa濃度の関係性は覚えておこう!
高Ca血症の原因
- 内分泌異常:副甲状腺機能亢進症など
- 骨異常:多発性骨髄腫など
また、副甲状腺ホルモン(PTH)の数値も関係するので、
- PTH高値:原発性副甲状腺機能亢進症、サルコイドーシス、異所性PTH産生腫瘍
- PTH低値:ビタミンD過剰症、悪性腫瘍に伴う高Ca血症
低Ca血症の原因
- ビタミンD欠乏症:腎不全など
- 副甲状腺機能低下症
- 急性膵炎
- 低アルブミン血症
低Ca血症の場合も同様に、副甲状腺ホルモン(PTH)の数値が関係するので、
- PTH高値:特発性副甲状腺機能低下症
- PTH低値:ビタミンD欠乏症
まだ余裕があるぞって方は、心電図変化も一緒に覚えよう!
Ca濃度による心電図変化
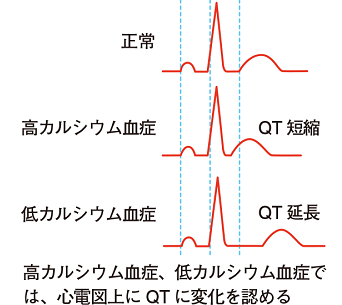
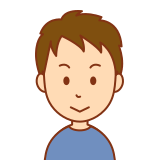
心電図変化も一緒に覚えると完璧だね‼
Mg(マグネシウム)とは
次に、Mg(マグネシウム)について解説していきます。
Mgは、骨を健康に保つために欠かせないミネラルで、神経の伝達、筋肉の収縮、酵素の活性化などに関与しています。
- 基準値:1.8-2.5mg/dl
体内には約25gのMgがあり、そのうち約50~60%は骨に蓄えられています。
Mgは腸で吸収され、その後、腎臓で再吸収・排泄されます。また、骨に運ばれて体の中で再利用されます。
食事から摂るマグネシウムの吸収率は、1日に300~350mg程度を摂取した場合、約30~50%です。ただし、摂取量が多すぎると、逆に吸収率は下がってしまいます。
高Mg血症の原因
- 排泄障害:腎不全
- Mgの異常投与
主な症状
- 吐き気・嘔吐
- 筋力の低下
- 低血圧
- 心拍の異常(不整脈や徐脈)
- 意識障害、昏睡(重症時)
- 呼吸抑制(特に高齢者や腎機能が低下している人で注意)
低Mg血症の原因
- 摂取・吸収障害:慢性アルコール中毒、下痢など
- 尿中のMg喪失:Bartter症候群、ケトアシドーシスなど
- 細胞内への移動:急性膵炎など
主な症状
- 筋肉のけいれん、こむら返り
- しびれ、ふるえ
- 疲れやすさ、虚弱感
- 不整脈(特に心房細動など)
- てんかん様発作(重度の場合)
- 低カルシウム血症や低カリウム血症を伴うこともある
Mg濃度による心電図変化
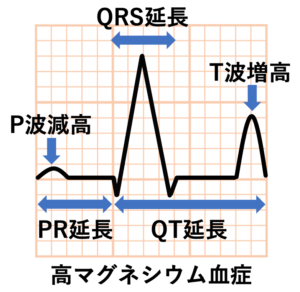
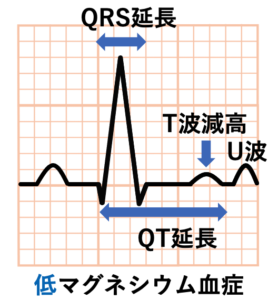
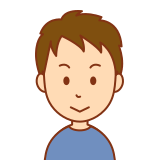
特徴が多いので、高Mg血症と低Mg血症で違う部分だけを覚えるのもポイントだよ!
まとめ
今回は、Ca(カルシウム)、Mg(マグネシウム)の2つを詳しく解説していきました。
前回よりも関連する項目が多いので覚えることは多いですが、一度覚えると点数を取れる範囲は広がるはずです!
電解質は国家試験でも必ず1問は出るので、前回のおさらいも含めて、重要なポイントを押さえて必ず点数がとれるようにしましょう!
前回のおさらいをしたい方はこちらをチェック✅
➤試験によく出る電解質をマスターしよう①
臨床検査技師国家試験の基本情報を確認しておきたい方は、こちらもチェック✅
➤【必読】臨床検査技師国家試験合格のための入門編①